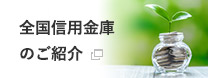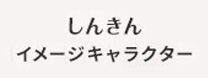個人賞
帯広信用金庫(北海道): 藤嶺 匡宏 氏
鉄道おもちゃのジオラマ展示活動
藤嶺氏は、長女と一緒に遊んだのをきっかけに、2001年頃から「鉄道おもちゃのジオラマ」(以下「ジオラマ」)制作を趣味として楽しむようになった。2002年1月、玩貝メーカーのトミー(現タカラトミー、以下「同社」)主催「フォトコンテスト」で長女と一緒に「すてきで賞」を受賞。2005年4月、地元百貨店で開催されたおもちや収集家のコレクションを展示する「第5回わらベフェスティバル」へ、催事企画の担当者から誘われ参加することとなった。動きのあるジオラマの展示は、想像以上に来場者から好評を得た。
この体験からジオラマの展示が多くの人に楽しんでいただけるコンテンツであるとの実感を得たため、主に同百貨店の催事企画(来客入場無料の条件で誘われた時)や公共施設などを中心に、年数回展示をするようになった。2009年7月、同社主催「プラレール50周年記念キャンペーン」で投稿写真が入賞。さらに2023年11月、同社主催「一畳プラレールコンテスト」では「大賞」を受賞した
展示会場に設置した来場者の感想ノートには、来場者から感謝や感動、励みになる言葉などが多数綴られていた。今後も本活動を通して、地域の方々に楽しんでいただける取り組みを続けていきたいと考えている。
-
2019年11月、地元小学校での展示会。多くの生徒が興味を抱き展示に引き付けられた。

青い森信用金庫(青森県): 石橋 晃寛 氏
八戸三社大祭 山車づくり技術の伝承
石橋氏は、幼少の頃より父親の影響で地元の山車組である十一日町龍組に、お囃子などで参加していた。社会人となり、山車製作にも参加。信用金庫職員を続けながら、山車製作の第一人者となった。
山車のデザイン・設計から、資金・人材・材料の調達、製作・組み立て、祭り期間の運行、メンテナンスまでをこなす職人兼山車組の総括・指導も行うマネージャーとして、山車製作期には、信用金庫の業務終了後や休日の深夜まで取り組む。地元ケーブルテレビ局の「八戸三社大祭」特集番組では、解説者も務める。
300年の歴史を誇る「八戸三社大祭」は、2004年に国の「重要無形民俗文化財」に指定、2016年ユネスコ無形文化遺産に「山・鉾・屋台行事」として登録された。石橋氏は、2021年4月から2023年3月まで「八戸三社大祭」運営事務局を務める地域連携DMOの「VISITはちのへ」に出向し、これまで培ってきた人脈やノウハウで貢献。4月当金庫に戻り、地方創生をミッションとする地域支援室に勤務している。
また、ワークライフバランスの実現に向け、仕事や家庭生活、地域活動などを両立しているロールモデルとして青森県八戸市ホームページで紹介されている。
-
2019年の最優秀賞を受賞した十一日町龍組の山車「楊貴妃」。八戸三社大祭の山車は、
歴史上の人物や軍記物、昔話や神話などが題材として選ばれ製作される。
栃木信用金庫(栃木県): 金子 裕之 氏
あらい水と緑の会での農村環境保全活動
金子氏は、本店営業部副部長として栃木信用金床に勤務する傍ら、家業である米麦の生産に携わり、砺木県(以下「県」)栃木市大平町新地区(あらいちく)の農地保全を目的とした地域団体「あらい水と緑の会」に12年前から参画。地域住民と共に、休日を中心にボランティア作業や伝統行事を運営している。主な活動は農道・水路・農用地の整備と生き物の保全、伝統行事の開催などである。参加者が年々高齢化する中、高齢者と若年層の架け橋として、農地担い手の育成や伝統行事継承のために、身を賭して活動を続けている。
この活動は、体力も必要で、地元住民の協力なしでは成り立たない。また近年は、台風や大雨の影響による苦労も多い。しかし、この活動がなければ、地域の環境は手当てされないまま荒廃し、暮らしにくい地域になってまう。農業はもちろん地域住民にとって、なくてはならない存在となっている。
また、地元小学校での田植え・稲刈り体験、どんど焼き・しめ縄作り・夏祭りなど地域の伝統行事を地域住民と一体となって開催している。
これらの活動は、農地保全や担い手の育成等、地域農業の将来に向けた画期的な活動であるとして、県が認定する「地域営農ビジョン」のモデル組織として当会が認定されるなど、高い評価を得る活動となっている。
-
子供たちに農業へ親しみを持ってもらうため、地元小学生の田植えを支援